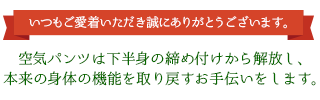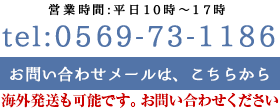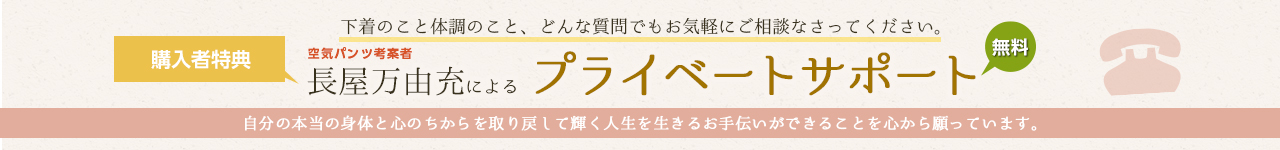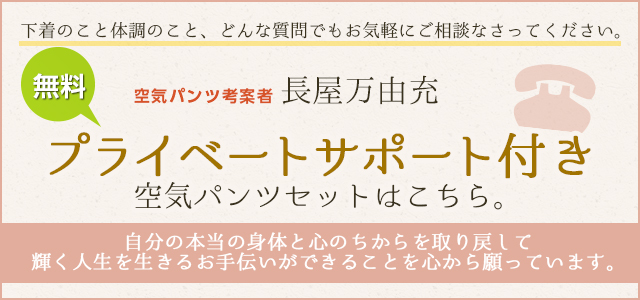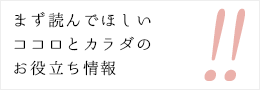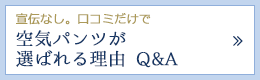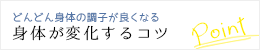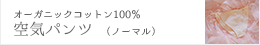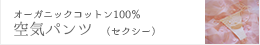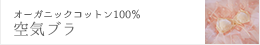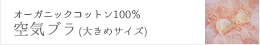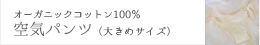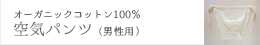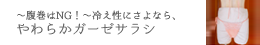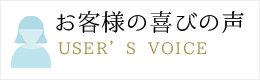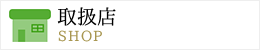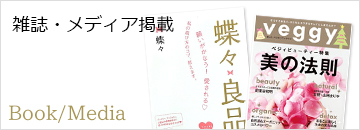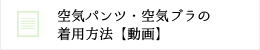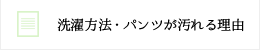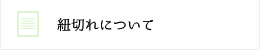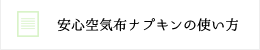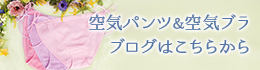アボリジニの伝統的な婚姻 No2 兄である少年を一時的に妻にする「交換」の概念って・・・・えーー(@_@;)
アボリジニを調査、研究した初期の民俗学者たちは、アボリジニの部族の間で若者が少年と結婚する少年妻の制度が広く普及していたことを報告しています。
アボリジニの若者は、割礼を含む一連の通過儀礼(イニシエーション)を終えると一人前のオトコとして認められて、結婚できるようになるのですが、彼が結婚する権利を持つ娘がまだ生まれていない場合、あるいは生まれていても、まだ幼くて結婚年齢に達していない場合には、娘と結婚できるようになるまでの間、その兄である少年を一時的に妻にする習慣があったというのです。
少年妻になるのは割礼前の少年で、この少年妻の制度にはメラネシアの部族の場合と同様, 少年が自分の体内にオトナの男の精液を受け入れることで、一人前の男になる通過儀礼の意味合いもあったようです。…
その結果、アボリジニの男性は、自分の妻の兄弟と男色関係を持つことが一般的になっていたそうです。
さらに娘と結婚する前に、その父親の「妻」になり、その父親と肉体系関係を持つ習慣もあったといいます。
このようなアボリジニの性行動は、われわれ現代人の感覚からすると随分と乱れているような印象を受けますが、必ずしもそうではなく、その行動は文化人類学でいう「交換」の概念に基づいた一定のルールに従っているのです。
この「交換」の概念は、アフリカのピグミー族やニューギニアなどメラネシアの部族、アマゾンのインディオなど未開部族によくみられる「姉妹婚」の習慣と密接に結びついています
近親婚を防ぐために結婚相手は別の集団から選ぶのですが、集団Aと集団Bに属する2人の若者が互いの姉妹を交換して結婚することになり、これを文化人類学で「兄弟=姉妹婚」と呼びます。
妻として差し出す姉妹がいない場合には、身内の若い娘を名目的な「妹」に仕立てて差し出すそうですが、アボリジニの少年妻の制度は、このギブ・アンド・テイクの「交換」の概念に基づいた兄弟=姉妹婚を敷衍したものといえます。父親が娘の婚約者の若者と肉体的関係を持つケースも同じ交換の概念と思われます。
日本でも平安時代の貴族は自分の妻の兄弟と男色関係を持つことが多く、
戦国時代の武将が寵童だった男に自分の妹や娘をめとらせるというようなこともよく行なわれていました。