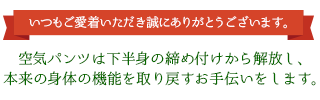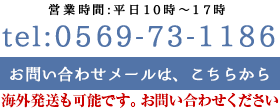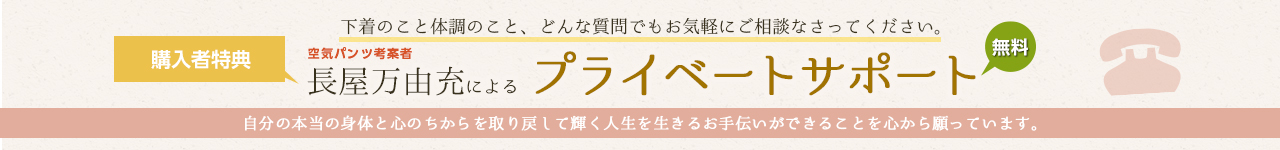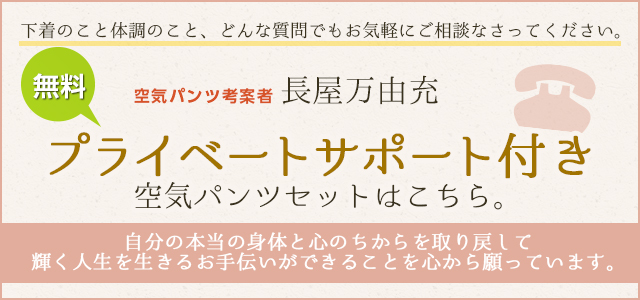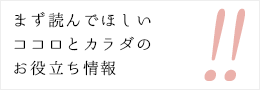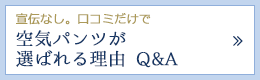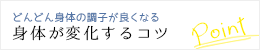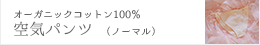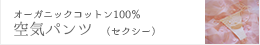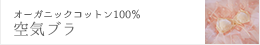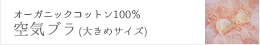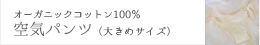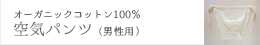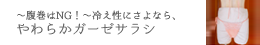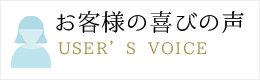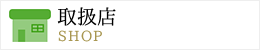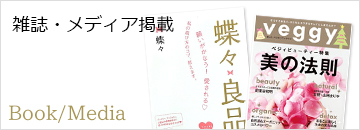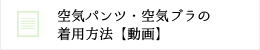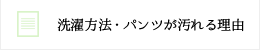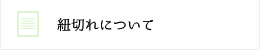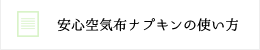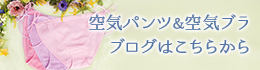日本での夜這いのならわし
日本では夜這いのならわしは、高度経済成長期直前まで各地に残っていました。
なかでも農村より漁村は、共同労働が多く、集団の結束が固かったため、夜這いのならわしが最後まで残っていたそうです。
夜這いのならわしは、村落共同体の崩壊と共に消滅しました。
明治政府が夜這いを「富貴紊乱(びんらん・・乱すこと)」の名の元に統制していきました。
夜這いについてさまざまに語らせてきましたが、
実際は、
共同体の若者による娘のセクシャリティ管理のルールであることがわかってきました。初潮の訪れと共に娘組に入り、村の若者の夜這いを受ける娘にとっては、処女の値打ちなどないし、童貞・処女間の結婚など考えられないものでした。
結婚の相手を見つけるときには恋愛関係のもとでの当事者同士の合意がなければ成り立ちませんでした。
ですから親の同意のもと、見たこともない相手に嫁ぐという仲人婚は村の夜這い仲間では考えられません。
夜這いには、若者にとっても娘にとっても、統制的な面と開放的な面の両面があったのです。
「お見合い結婚」や「女性は処女のまま初夜を迎える」といった「伝統」は、ほんの近い過去に出来上がったもので、「伝統」ではなかったのです。
明治政府が夜這いを取り締まろうとしたとき村の若者たちは「夜這いがなくなるとどうやって結婚相手をみつけたらよいかわからない」と言って反対したそうです。